【ソルジャー採用とは?】原則ありえない理由とやってる会社
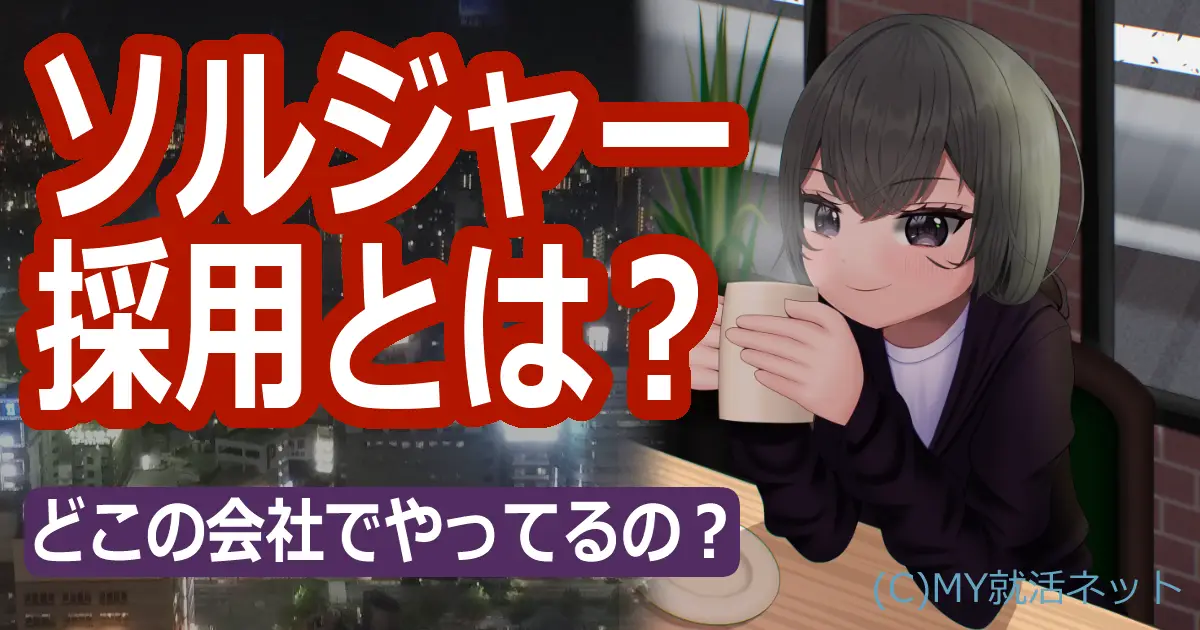
「自分の出身大学ではソルジャー要員ではないか」と不安に思うかもしれません。 この記事では「ソルジャー採用とは何か」「それが原則ありえない理由」を解説します。 結論、「総合職」で入社する限り「ソルジャー採用」ではありません。
おすすめ・人気記事
ソルジャー採用とは?
ソルジャー採用とは、あらかじめ出世を前提としない「平社員要員」としての採用。
「ソルジャー(soldier)」とは本来、将校の指揮のもとで任務を遂行する兵士や下士官を意味します。
就活においては、この言葉が転じて、管理職にはなれず、現場で働き続ける社員を意味するようになりました。
就活で使われる「ソルジャー」の意味
以下のような特徴をもつ社員が、ネット上などで「ソルジャー」と呼ばれることがあります。
- 営業職などの現場に長くとどまる
- 昇進がほとんど期待されていない
- 幹部候補生として扱われない
特に以下のような業界で噂されることが多いです。
- 銀行
- 証券会社
- 大手メーカー
学歴によるキャリアの分かれ目?
掲示板などでは、以下のような区分がされているという声もあります。
| 学歴 | 役割 |
|---|---|
| 旧帝大・早慶上智・MARCH・関関同立・上位国公立 | 幹部候補(将来の管理職) |
| それ以外 | ソルジャー要員(出世しない社員) |
このように、「学歴によって出世の有無が決まる」といった話から、「ソルジャー採用」という言葉が使われるようになりました。
なぜソルジャーになる人が多いのか?
企業では、誰もが管理職になれるわけではありません。出世の過程は非常に厳しく、次のような段階を経てふるい落とされていきます。
- 課長昇進:前後5年の社員の中でも特に優秀な人のみ
- 部長昇進:課長の中でもさらに限られた精鋭
- 役員登用:部長の中でもごく一部
出世競争に敗れた残りの社員は「名ばかり管理職」というソルジャーになります。
原則ありえない理由
ネット上では、「出世しない平社員(ソルジャー)を最初から選んで採用している会社がある」といった噂が出回っています。 しかし、現実の企業活動において、「ソルジャー採用」が実施されている例は極めて稀です。 以下では、その理由を論理的に解説します。
社員の8割は自然にソルジャー化する
| 理由1 | 勝手にソルジャーになる |
|---|
企業では、管理職に昇進できる社員はごく一部に限られます。 課長に昇進できるのは同期入社の中でも数%、そこから部長・役員になるにはさらに厳しい競争があります。
つまり、大半の社員は自動的に出世コースから脱落し、現場にとどまる=「ソルジャー」になるのです。 企業側はあえて平社員要員として人を採用しなくても、構造上そうなる仕組みになっています。
ソルジャー社員は企業にとって負担
| 理由2 | ソルジャーはお荷物 |
|---|
近年、多くの企業で早期退職や希望退職の対象となっているのは、成果を出せない中間管理職=ソルジャー化した元出世候補です。 こうした人材はコストだけが高く、経営に貢献しにくいため、企業としては増やしたくないのが実情です。
そのため、最初から出世しないことを前提としたソルジャー要員を採用するなど、本末転倒な戦略を企業が取る理由はありません。
将来の幹部候補は、入社段階では見抜けない
| 理由3 | 入社後学歴は関係ない |
|---|
「この人はソルジャー」「この人は幹部候補」と入社時に線引きするのは不可能です。 なぜなら、本当に優秀な人材は、学歴や経歴では測れない要素を持っているからです。
実際に私が在籍していた企業では、高卒の現業職社員が、旧帝大卒の社員を差し置いて課長にまで昇進した例がありました。 その社員は、仕事に誠実で、自ら学び続け、責任感と使命感をもって業務に取り組む人物でした。
このような「将来のエース」は、どんな学歴や初期スペックよりも、入社後の成長意欲と適性によって評価されるべき存在です。 採用段階でそういった人物を見逃すことは、企業にとって致命的な機会損失です。
まとめ:企業が採用で本当に見ているもの
企業は、応募者を「ソルジャー要員」として線引きするのではなく、誰にでも成長のチャンスがあるという前提で人材を採用しています。
だからこそ、「自分は学歴が低いから」「出世は無理だろうから」と最初からあきらめる必要はありません。 本当に求められるのは、入社後にどう成長するかです。
実施している会社とは?
ソルジャー採用を実施している会社も、実際に存在する!
原則として「ありえない」ソルジャー採用ですが、火のない所に煙は立たぬと言います。 実は平社員前提で採用される職種・区分が存在する企業があります。
「総合職」と「エリア総合職・現業職」の違い
ソルジャー採用が行われている代表的なパターンは、企業が新卒採用で以下のような区分制度を設けている場合です。
| 職種区分 | 出世の可能性 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総合職 | あり(幹部候補) | 全国転勤あり。部長・役員など全社の経営に関わるポジションに昇進可能。 |
| エリア総合職 | 限定的 | 転勤なし。課長までは可能でも、部長・役員クラスは対象外。 |
| 現業職 | 基本的になし | 与えられた業務をこなす現場中心。管理職登用の前提がない。 |
転勤を拒否するエリア総合職では、全社的な経営判断や大規模な異動を伴う経験が得られないため、幹部登用に必要な視野や経験が不足しやすいのです。
また、現業職は「指示された仕事を遂行する」ことが主目的であり、ビジネス視点や経営的視野を養う機会が極めて限られるため、昇進前提での育成対象ではありません。
ソルジャー採用を行っている企業の具体例
以下のような企業では、エリア総合職・業務職といった昇進の制限がある職種を採用しており、事実上の「ソルジャー採用」と考えられます。
- JRグループ:JR東日本、JR東海、JR西日本の「エリア総合職」「プロフェッショナル職」
- メガバンク:三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行の「エリア総合職」
- 総合商社:三井物産の「業務職(=エリア職)」
- 証券・保険業界:大和証券、野村證券、保険会社各社
- インフラ企業:関西電力など
「総合職のみ採用」の企業はソルジャー採用なし
一方で、すべての新卒を「総合職」として採用し、職種や勤務地の制限を設けない企業では、入社後の実力次第で誰でも幹部候補になれるため、ソルジャー採用の構造は存在しません。
実力での昇進が可能な人材を求める企業にとって、わざわざ出世しない社員を前提に雇う理由はないのです。
ソルジャーになる人の特徴
私が会社を見渡してきた中で、ソルジャーになる人の特徴を3つ発見しました。
特徴1:仕事を「嫌なこと」と捉えている
総合職として採用されるということは、将来的にビジネスの中核を担うことが期待されているということです。 そのため、「仕事=我慢するもの」「早く終わらせたいもの」といった意識を持っている人は、なかなか評価されづらくなります。
もちろん、仕事には面倒なこともあります。それでも、ビジネスの仕組みや成果を自分ごととして捉え、主体的に関わる姿勢が求められます。
一方で、出世する人たちは日々の業務に強い関心を持ち、退勤後にも自然と「どうしたらもっと良くなるだろう」と考える習慣があります。 たとえば営業であれば、「どうすれば顧客に喜んでもらえるか」「より効果的に提案する方法はないか」と試行錯誤し続けるのです。
そして、自ら学び、実践することで自然と周囲の信頼を得て、チームを引っ張る存在へと成長していきます。
私は人事部に在籍したこともありますが、社内研修のテーマは「社員に主体性を持たせる」ことでした。 若手に「主体性」を持たせることで、「将来のソルジャー化を防止したい」という思惑がありました。
特徴2:「仕事の範囲」を狭く捉えている
「これは他部署の仕事だから」「自分の業務ではない」といった姿勢は、ソルジャー的な働き方に繋がりやすいものです。
幹部候補として期待される人物は、自分の所属を超えて会社全体の動きを理解しようと努めます。 たとえ事務系の職種であっても、商品知識や技術の背景を知ろうとする姿勢が、顧客からの信頼を生みます。
もちろん、業務には所掌があり、すべてを完璧にこなすのは困難です。 しかし、「背景を理解しようとする」「他部署の視点で考える」だけでも、大きな違いが生まれます。
そうした広い視野を持つ人材は、部門を超えた連携やリーダーシップを発揮しやすく、将来的なマネジメント層として期待されるのです。
私が最初に配属された部署では「技術的な知識を身につける」ことを否定されていたのですが、 出世頭の社員は勝手に技術を勉強していました。それが顧客の信頼獲得につながり、高い成果を上げていたのです。
特徴3:給料に対して不満ばかり口にする
給料に対する関心は誰にでもありますが、不満を口にするだけで終わってしまうのは、評価されにくい行動です。
企業は限られた利益の中で報酬を分配しています。 経営状態を知るためには、会計書類に目を通すことも必要です。たとえば「なぜ黒字でも昇給が難しいのか」「利益率がどう変化しているのか」などを理解することで、給与の背景も見えてきます。
出世する人材は、単に報酬を求めるのではなく、「利益をどう増やせばいいか」を自分で考えます。 そのために営業戦略を見直したり、商品価値を高めたりと、積極的に行動を起こします。
結果として、組織にとって不可欠な存在となり、適正な報酬が自然と与えられるのです。
簡単に言い換えると、高く売らないと給料は上がらないということです。 「高く売る社員」は評価が上がり、その人だけボーナスが増額されます。
ソルジャーにならないために——未来は自分で選べる
「もしかして自分の大学ってソルジャー枠……?」「出世なんてできないのかな……」と不安な人もいるかもしれません。 ですが、安心してください。ソルジャーになるかどうかは、大学名で決まるものではありません。
確かに、企業によっては採用時点で「総合職」「エリア職」といった区分を設けている場合もあります。 ですが、本当に求められているのは、ビジネスを自分ごととして考え抜ける人です。
あなたがどんな大学を出ていようと、「課長じゃないけど課長の代わりにやってやる」という覚悟があれば、会社は必ず見ています。 むしろ、そういう人こそ本当に尊敬され、引き上げられるのです。
仕事を面白いと思えるかどうか、自分で勉強し、行動できるかどうか。それだけです。 誰でも最初は不安ですし、何が正解かもわかりません。でも、自分の頭で考え、動き、価値を生み出す——その経験が、あなたを唯一無二の存在に変えていきます。
大丈夫。あなたはソルジャーにならない。 今この瞬間から、自分で選び、自分で動く。その一歩が、全てを変えていくのです。
→会社とは?|部署・役職・出世事情などの仕組みを知ろうの記事へ戻る