【ガクチカ】リーダーシップ経験の例文7選|肩書は不要!
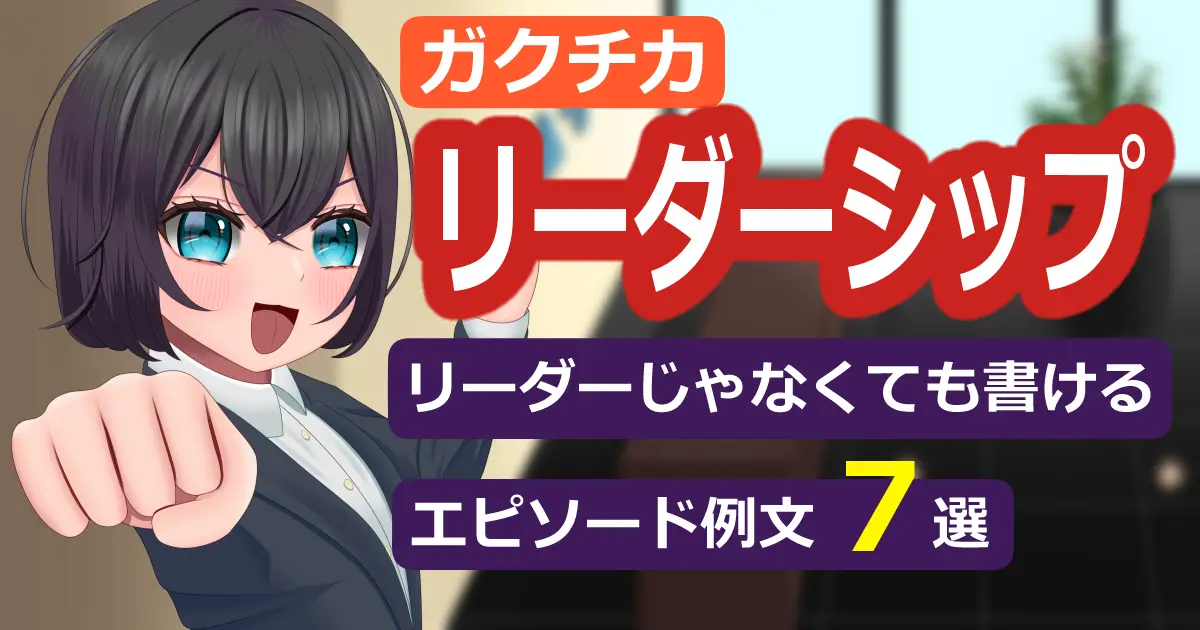
ガクチカに関連して話す「リーダーシップ経験」の例文を7つ紹介します。 「リーダーじゃない」人でもアピールできるよう、すべて「肩書なし」で書いています。自己PRなどに役立ててください。
目次
おすすめ・人気記事
リーダーじゃないけどリーダー経験が書ける?
| 結論 | 肩書は不要 |
|---|
リーダーじゃなくてもリーダーシップ経験は書けます。
むしろ「バイトリーダー」「サークルリーダー」などは「やらされたこと」にカウントされるため、 肩書自慢で終わったら「主体性がない」として落とされます。
実際、私が参加したグループ面接では「バイトリーダー」をアピールする学生がいたのですが、 「バイトリーダー」の肩書が出た瞬間に面接官がダルそうに姿勢を崩し、 何も深掘り質問をせずにスルーしたのが強烈に印象に残っています。
面接官が聞きたいのはリーダーらしいエピソードであって、「肩書」ではありません。 逆に言えば、エピソードがあればリーダーじゃなくてもいいというわけです。
どんなエピソードを書けばいい?
| 結論 | みんなを活躍させたこと |
|---|
「リーダーシップ」と言われると、「みんなに指示命令をした」「自分の意見に従わせた」ようなイメージを持ってしまいがちですが、そうではありません。
必要なのは、チームのメンバーを活躍させたエピソードです。
実際、会社の「課長」や「部長」の役割は平社員を活躍させることです。 全員の仕事がうまくいくように、進捗管理をしたり相談に乗ったりします。 管理職は営業や設計を直接しません。なぜなら、「活躍させる人」であって「活躍する人」ではないからです。
実際には「プレイングマネージャー」といって管理職が実務をする場合も多いのですが、 それは学生も同じです。自分もがんばりつつ、みんなを活躍させたエピソードが重要なのです。
例文
リーダーシップ経験は、ガクチカの「直面した困難と乗り越えた方法」として書きます。 ここでは次に挙げるエピソードについて、それぞれ例文を紹介します。
- 意見対立を解消した経験
- チームの士気を向上させた経験
- チームの弱点補強をした経験
- 期限に間に合わせるための進捗管理の経験
- メンバーの適材適所を実現した経験
- 冷静なトラブル対応の経験
- 新しい取り組みを導入した経験
この記事では「リーダーシップ経験」にフォーカスしていますが、 ガクチカ全体の書き方については次の関連記事をご覧ください。
意見対立を解消した経験
| テーマ | ゲーム制作のサークル活動 |
|---|---|
| 困難 | 意見対立 |
取り組みの中で、「ストーリー性を重視する」か「ゲーム性を重視する」かで意見対立が発生しました。 これに対し、SNSを通じた市場調査のデータを踏まえ、前者の選択へと誘導しました。 この際、反対意見にも共感を示すことで衝突を防止することを意識しました。
ここでのポイントは、「メンバー同士の衝突防止」です。 「全員を活躍させる」ため、反対意見も褒めて「ゲーム制作という本業」で力を発揮できるようにしたのです。
「サークルリーダー」などの肩書はありませんが、理想の上司を振舞っているので問題ありません。
チームの士気を向上させた経験
| テーマ | 飲食店のアルバイト |
|---|---|
| 困難 | チームの士気向上 |
居心地の良い空間づくりを目指す取り組みの中では、「業務効率を優先すべき」との意見もありました。 そこで、SNSの口コミを分析し、雰囲気の良い店舗ほど評価が高いことを共有。 さらに、スタッフ同士が感謝を伝え合う仕組みを提案し、小さな成功を認め合う文化を醸成しました。
ここでのポイントは、「チームの雰囲気づくり」です。 ただ「がんばらせる」のは「イヤな上司」ですから、褒めたり夢を語ったりして「その気にさせる」のが理想の上司です。
実際、筆者の私も上司から「この案件やりたいよな。これ取ったらデケえ顔できるもんな。」と言われて、 「やりたいです!」とその気にさせられた経験があります。
また、アルバイトをテーマにしたガクチカの書き方と例文を、次の関連記事でも紹介しています。
チームの弱点補強をした経験
| テーマ | 映画研究のサークル活動 |
|---|---|
| 困難 | チームの弱点 |
映画制作サークルで、ストーリーを作れるメンバーが不在という課題がありました。 そこで、私は過去の名作を分析し、ストーリーの型を学ぶ勉強会を企画。さらに、メンバーのアイデアを引き出せるよう、ブレインストーミングの場を設けました。 すると、各自の発想を組み合わせる形で脚本が完成。チーム全体の創作力が向上し、作品の完成度も上がりました。
ここでのポイントは、「メンバーのアイデアを引き出す」ことです。 自分1人が優秀なだけでは、それは「平社員」です。みんなを活躍させるのがリーダーですから、 アイデアを引き出すための勉強会・ブレインストーミングの企画がこのエピソードの肝です。
実際、私の上司も平社員時代から頻繁に「勉強会」の企画をしてくれて、簿記やマーケティングなどを教わりました。 その人は後に「高卒最年少」で課長になりましたが、今でも理想のリーダーだったと思います。
期限に間に合わせるための進捗管理の経験
| テーマ | ハンドメイドのサークル活動 |
|---|---|
| 困難 | 期限の逼迫 |
イベント出展に向けた制作が遅れがちになっていました。 そこで、私は進捗管理を徹底するため、メンバーごとに目標を設定し、週ごとの進捗共有を実施。さらに、得意分野ごとに作業を分担し、負担を軽減しました。 締切前には作業会を開き、互いにサポートしながら効率を向上。結果として、全員が期限内に作品を仕上げ、無事にイベントへ出展できました。
ここでのポイントは、「目標設定と仕事量の調整」です。 作業の速い人・遅い人はどうしてもいますから、一律のノルマを課すのではなく、 メンバーの得意・不得意を見極めて、それに応じた目標を設定するのです。
自分が1人で解決してしまってはいけません。あくまでメンバー全員が達成感を味わえることが重要です。
メンバーの適材適所を実現した経験
| テーマ | 介護のボランティア活動 |
|---|---|
| 困難 | 業務負担の偏り |
業務の偏りにより一部のメンバーに負担が集中していました。 そこで、私はメンバーの得意分野や性格を踏まえ、話し相手が得意な人はレクリエーション、体力に自信がある人は移動補助を担当するなど、役割を再編成。 結果、各自が自分の強みを活かせる環境が整い、作業効率が向上。利用者との交流も活発になり、全員がやりがいを持って活動できるようになりました。
ここでのポイントは「メンバーの得意・不得意を見極める」ことです。 「全員を活躍させる」という観点では、やはり「自分が負担を肩代わりする」のではいけません。 「鈴木君はこれが得意だよね」と、単なる負担の分散ではなく「得意分野をやらせる」ことで、さらなる活躍が期待できます。
実際、会社の人事はそういう仕事をしています。 人事が普段心がけているのと同じことを、ガクチカでアピールできたら強いですね。
冷静なトラブル対応の経験
| テーマ | 大学のゼミ活動 |
|---|---|
| 困難 | 発表資料の消失 |
ゼミ活動で発表直前に資料データが消失するトラブルが発生しました。焦るメンバーを落ち着かせ、私はすぐに役割を分担。 記憶を頼りに要点を洗い出し、過去の資料やメモを活用しながら急ぎで再作成しました。 また、発表時はスライドが簡略化された分、口頭での説明を強化するよう提案。結果、無事に発表を終え、教授からも「冷静な対応が素晴らしい」と評価を受けました。
ここでのポイントは「メンバーへの気づかいと即座に役割分担する」ことです。 トラブル発生時は「犯人探し」をやってしまいがちですが、それを「即作業に取りかからせる」ことで未然に防止したのです。
チームの雰囲気を良くし、目標達成(発表に間に合わせること)に向かわせるのが理想のリーダーです。
また、学業をテーマにしたガクチカの書き方と例文を、次の関連記事でも紹介しています。
新しい取り組みを導入した経験
| テーマ | 飲食店のアルバイト |
|---|---|
| 困難 | 予約管理のミス |
飲食店のアルバイト先で、手書きの予約管理がミスや二重予約の原因になっていました。 そこで、私は無料の予約管理アプリを調査し、店長に提案。導入にあたってマニュアルを作成し、スタッフへの操作説明も行いました。 結果、予約管理がスムーズになり、業務効率が向上。ミスも減少し、スタッフの負担軽減につながりました。この経験を通じて、IT技術の活用が現場の課題解決に貢献できることを実感しました。
ここでのポイントは「メンバーが仕事ができるための取り組み」です。 例ではマニュアル作成や操作説明を挙げていますが、「ITリーダーに任命された」などは書かないほうがよいでしょう。 任命されたとたんにそれは「やらされたこと」になり、「主体性がない」と判断されてしまいます。
実際、私の上司はマニュアル作成を重要な仕事と位置づけていました。 なぜなら、全員が一定の活躍ができるようになるからです。
自己PRに使える重要ポイントのまとめ
| ポイント | 理想の上司 |
|---|
ここまでで解説した「リーダーシップ経験を語る上での重要ポイント」は、自己PRに使えます。
- みんなを活躍させること
- チームの雰囲気を良くすること
- メンバーのアイデアや得意分野を活かすこと
- 相談に乗ったり教えたりすること
例えば「私の強みは『みんなを活躍させること』です」から例文のようなエピソードを話すと「リーダーシップのアピール」になります。
気を付けてほしいのは、エピソードを話すことであって肩書自慢は落ちる原因になるということです。 特に「バイトリーダー」のような「店長から与えられた仕事」の話をしてしまうと、一発でアウトです。 時には肩書は伏せておいて、リーダーらしいエピソードだけを話すというテクニックも有効になります。
また、次の関連記事ではエントリーシート全体で「社風への共感」に説得力を持たせる方法を解説しています。 165社の深掘り質問を分析し、その対策を盛り込んだ内容になっていますので、ぜひご覧ください。