【参入障壁の高い業界9選】安定ホワイトって本当?
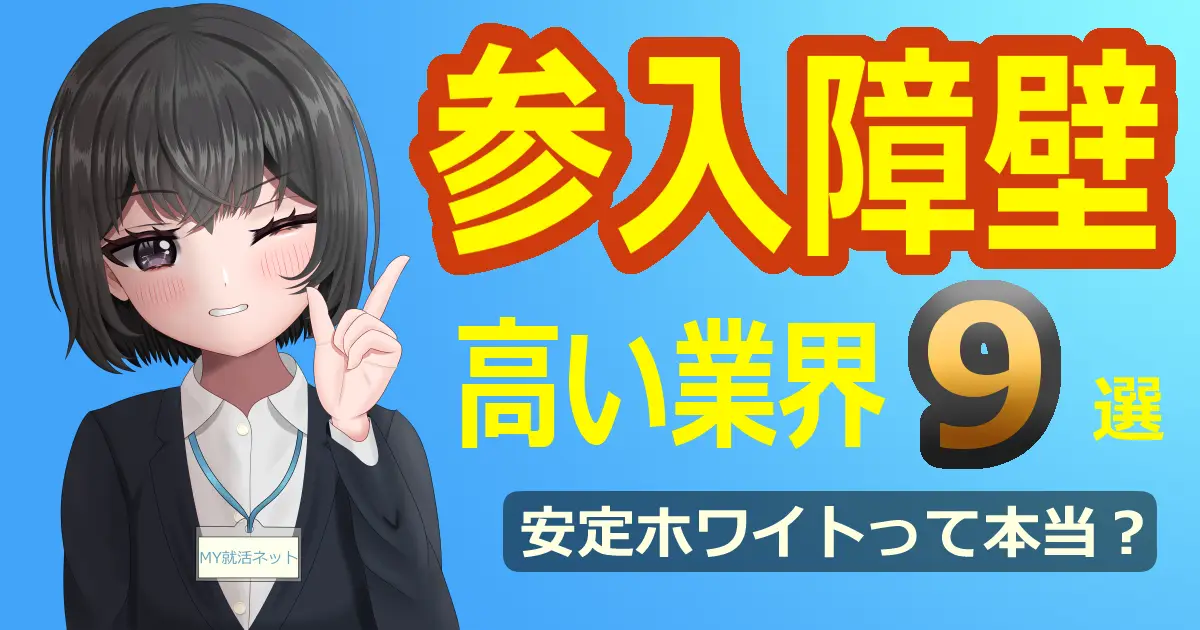
参入障壁の高い業界とは、どんな業界でしょうか。そしてそれらは本当に安定ホワイト業界なのでしょうか。この記事ではその例・メリット・デメリットを解説します。
この記事の要点
- 参入障壁とは、新たなライバルが現れない理由のこと!
- 主にインフラは、参入障壁が高い!
- メーカーも企業努力によって参入障壁をつくれる!
- 参入障壁があっても、ホワイト企業とは限らない!
おすすめ・人気記事
参入障壁とは
参入障壁とは、新たにライバルが現れない理由のこと!
参入障壁とは、「同じビジネスを新しく始めることを困難にしている原因」を意味する言葉です。 例としては「法的規制による市場独占」「政府のバックアップ」「企業努力による優位性の確保」があります。
参入障壁に守られた既存企業にとっては「価格競争が起きない」というメリットがあり、高い利益を確保することができます。 そのような企業に就職すると「高い年収」が期待でき、経営が安定することから「長く働くことができる」というメリットがあります。
一方で新規参入したい企業にとっては、法改正・政策の変更・既存企業以上の企業努力など高いコストがかかります。 それだけの努力をして参入に成功したとしても、今度は既存企業との価格競争が始まりますから、参入するメリットがないということになります。 特に「法的規制」「政府のバックアップ」による参入障壁の場合、「価格が高い」「競争がないので成長しない」などといった批判に晒されます。
参入障壁の例
参入障壁の例を、以下の表にまとめました。
| 法的規制による市場独占 | 地域や電波帯などを特定企業に割り当て、それ以外の企業の事業活動を禁止します。 例えば電力業界・テレビ業界・携帯キャリアが当てはまります。 |
|---|---|
| 政府のバックアップ | 事業を始めるのにかかる莫大なコストを政府が負担し、支援の受けられない会社は実質その事業活動を行えません。 また政策で寡占市場・独占市場が許されている業界もあります。 前者は高速道路業界・JR各社・NTT東西が当てはまり、後者は日本製鉄など高炉メーカーが当てはまります。 |
| 企業努力による優位性の確保 | 特許の取得・早期の量産体制の構築・技術のブラックボックス化などによって、 他社が追随できない高みに上ってしまう方法です。 例えば化学メーカー・機械メーカー・電機メーカーなどが得意としています。 |
参入障壁の高い業界
参入障壁の高い業界は、次の9業界が挙げられます。
これとは別に、「たばこ」も参入障壁があります。たばこ葉を育てるには国の許可が必要です。 JTの他、海外のたばこ会社があるのみで、日本で新しくたばこ会社を設立することは不可能です。
電力業界
電力業界は、地域独占が認められている!
電力会社が最たる例でしょう。電力業界に新規参入することはできません。
「電力小売り」「発電事業」がそれぞれ自由化されていますが、必ず既存の電力会社を通さなければなりません。 電力は「安定供給」が最重要項目であり、原子力発電や火力発電のバックアップなしには成立しないためです。 「電力小売り」では電力会社に「仕入れ代金」を支払わなければなりませんし、「発電事業」では電力会社に「売電」しなければなりません。
「新電力」と呼ばれる企業群は新規参入したかのように見えますが、 結局のところ電力会社のもつ送電網に頼らざるを得ず、加えて電気は「どの発電所の電気か」を区別できません。 そして安定供給のために、既存の電力会社のバックアップを受けているのが現実です。
電力会社は複数ありますが、エリアごとに分かれています。 許可を受けたエリアで発電し、送電するので基本的には他の電力会社とエリアが被ることはありません。 そのためその地域では独占企業となるわけです。
また、特に電源開発は発電特化型の電力会社ゆえに、消費者との直接取引がなく、 他の電力会社に比べて知名度が低めです。就活においても知る人ぞ知る優良企業です。
テレビ業界
テレビは電波の余りがないので新規参入できない!
国の許可が必要と言えば、テレビ放送も参入障壁が非常に高く、新規参入が不可能です。 というのも、テレビ放送に使える電波帯は決まっており、余りがないからです。
東京ならフジテレビや日本テレビ、大阪なら読売テレビや毎日放送など、 テレビ局の数が限られています。その少ない電波を、今あるテレビ局で独占している状況です。 「既得権益」などと政府批判をしがちなテレビ業界ですが、実は自分自身が最強の既得権益なんですね。
通信業界
携帯電話も電波の余りがないので新規参入できない!
通信業界の中でも、携帯キャリアは「法的規制」による参入障壁に守られています。 電波帯の利用許可を取らなければならず、加えて大量の基地局の建設が必要なことから、新規参入は非常に難しい業界です。 本来なら、旧国営企業のNTTドコモの独占になると思われていました。
ところが現実には、トヨタと京セラを後ろ盾にしたKDDIや強烈な経営力をもつソフトバンクの参入があり、 さらには政府肝いりの楽天も参入しました。 これは後発3社が莫大なコストをかけて規制緩和・大規模設備投資を行ったために実現したことで、参入障壁が突破された稀有な例だと言えます。
NTT東日本・NTT西日本は、「法的規制」の恩恵はありません。 しかし一方で、国営時代に築いた固定回線網が巨大な資産となっており、「政府のバックアップ」によって独占的地位を築いた企業群と言えます。
各携帯キャリアの基地局はNTT東西の固定回線を通じてインターネットに接続されますから、 結局のところすべての通信会社がNTT東西に依存することになっています。
公共事業
公共事業の実績がないと、公共事業ができない!
実は建設業界も高い参入障壁があります。
国や地方自治体相手の仕事といえば、競争入札になります。競争入札は「価格」だけでなく「企業評価」も大きな配点を占めているのですが、 その「企業評価点」を大きく左右するのが「施工実績」です。 簡単に言えば、似た内容の公共工事の実績がないと、公共工事を落札できないというわけです。
そう、公共工事をやったことがない新規事業者は、公共工事をすることができないのです。
「実績がないとできない」という業界の特殊な事情があまり知られていないため、 大半の就活生はスーパーゼネコン以外をスルーしてしまいます。 特に準大手ゼネコンは平均年収が900~1000万円ある一方で競争倍率が10倍程度しかない穴場になっています。
鉄鋼業界(高炉)
高炉建設は費用が莫大すぎて新規参入できない!
鉄鋼メーカーのうち特に「高炉メーカー」も非常に参入障壁の高い業界です。 これは国の許可が必要なわけではなく、開業に必要な資金が莫大すぎるためです。
国内トップの日本製鉄は「官営八幡製鉄所」をルーツとしており、明治政府が国策でつくった会社です。 2位のJFEスチールも川崎重工業や浅野財閥といった巨大資本をルーツにしています。
一度工場見学に行ってみるとわかると思いますが、工場の規模がもはや町レベルです。 ドラマ「華麗なる一族」でも高炉建設に奮闘していましたが、 電炉メーカーという下地があっても高炉の建設には常識では考えられないほどの投資が必要なのです。
問題はそれだけではありません。日本製鉄は長らく世界最大の鉄鋼メーカーでした。 それが近年、M&Aで大きくなったアルセロール・ミッタル、中国宝武鋼鉄集団、河北鋼鉄集団に抜かれ、 現在4位に位置しています。
これを受けて日本製鉄も国内で買収を進め、吸収したりグループ会社に加えたりしています。 ほとんどの鉄鋼メーカーが日本製鉄かJFEスチールの傘下に入っていますので、 実質この2社しかないといっても過言ではありません。
→【日本製鉄の就職】難易度|早期選考・面接に役立つ「強み」を解説
鉄道業界
鉄道はいまさら土地の確保が困難!
鉄道業界も参入障壁が高いと言えます。 路線の新設には許可が必要な上に、あまりに広範すぎる用地買収を行わなければなりません。
国鉄をルーツにもつJR各社は、「政府のバックアップ」によって鉄道路線を敷いてきました。 今さら政府支援での路線の新設などできませんから、あまりに高すぎる参入障壁だと言えます。
一方の私鉄は「政府のバックアップ」を受けていませんが、 国土開発が進む前、人口増加の流れに乗って路線を建設してきたのであり、 今さら同じ方法で鉄道会社を新たに作ることなどできません。
また「新設の許可」では「路線の並走」があまり認められてこなかったことから、 他社と競合することも少なく、各社が共存共栄を図れる仕組みになっています。
高速道路業界
高速道路も建設資金の確保が不可能!
高速道路業界も参入障壁が高いです。 現在の高速道路は、旧道路公団の時代に莫大な費用をかけて建設されたものです。 民営化直後は40兆円もの負債を抱えており、現在はその返済途上です。
道路建設自体は特に法的規制はなく、ルール上は新規参入が可能です。 ですが「用地買収」「建設」にはあまりに膨大過ぎるコストがかかりますから、 やはり新規参入は事実上不可能と言わざるを得ません。
化学メーカー
化学メーカーは、発明を即座に量産化して追いつけない高みに登る!
化学メーカーの参入障壁は、「企業努力による優位性の確保」によるものです。
半導体材料・電子部品に関しては「超高純度」などの非常に高い技術力が求められ、 いち早く実現した会社はすぐに量産体制を構築します。
すると後発の企業が新たに研究開発をしても価格競争になり、研究開発費を回収するほど儲からないことが予想できます。 ですから「一番乗り」の企業に譲って他の製品の開発で勝負するのです。 ゆえに独占的シェアを取る製品群をもつ企業が非常に多く、高い利益・高い年収といった高待遇を実現しているのです。
機械メーカー
機械メーカーはあえて特許を取らず、「謎技術」のままにしておく!
機械メーカーの参入障壁も、「企業努力による優位性の確保」によるものです。
この業界は「特許を取る」ことよりも「技術をブラックボックス化する」ことで、後発企業の追随を防いでいます。 特許権は25年で失効しますから、あえて特許を取らないことで秘密の技術にしておくというわけです。 こうして「未だに解明されていない技術」を1社で独占していて、独占的シェアを実現できるという仕組みになっているのです。
例えばDMG森精機や島精機製作所が、 部品の内製化を徹底して技術流出を防ぎ、かつ特許を取らないことで唯一無二の地位を維持しています。
参入障壁のメリット
参入障壁のメリットは、次の3点です。
- 経営が安定する
- 社会貢献度が高い
- 年収が高い
最も大きいのが、「経営が安定する」ことです。 独占市場となることで、利益は守られ、雇用も守られます。参入障壁に守られた企業はメリットを享受します。
実は、一般消費者や他の業界にもメリットがあります。
例えば電力会社の場合、電力会社が最優先しなければならない業務は「電力の安定供給」です。 停電が起こればあらゆる工場が止まり、パソコンは強制シャットダウンします。経済活動が停滞するのです。
飲食業界のように過当競争になってしまうと、品質が低下します。 安さを追求した結果食中毒を引き起こすように、電力業界が価格競争で疲弊すれば、停電が予想されます。
参入障壁を作り、電力会社にお金の心配をさせないことで、安定供給を可能にします。 電気を使う人みんなが、参入障壁の恩恵を享受しているのです。
鉄道や高速道路も、参入障壁によって品質が確保されています。簡単に崩壊するような線路や道路では困るのです。 それでも事故がないわけではありませんが、自由競争だった場合はもっと不便な世の中になっているはずです。
参入障壁のデメリット
参入障壁のデメリットは、次の5点です。
- サービス・製品の値段が高くなる
- サービス・製品の質の向上がない
- ホワイト企業とは限らない
- 将来性に乏しい
- 昭和の体質が残りがち
値段が高くなることと、サービスの向上がないことは不可分一体です。 競争がない分、価格競争もサービス向上競争も起こらないのです。そのため、値段は高く、サービスは悪いという状況が発生しがちです。
日本の電気料金は海外に比べて高く、新幹線や高速道路の料金も高いままです。 公定料金となるため、割引や値引きも自由にはできません。独自性も出しにくく、サービスの向上は望めません。
さらに何もしなくても利用客が大勢いるという状況も、 サービス向上を阻害する要因です。安定して利益が見込めるため、 利益を増やすための挑戦や努力がなくても、会社としては生き残れるのです。
殿様商売が可能であり、利用客に対し横柄になりがちです。 「嫌なら使わなければいいんじゃない?」という態度が取れますが、 利用客はその会社のサービスを利用せざるを得ません。
また新規参入ができないため、新たなサービスを思いついた人がいても、 そのサービスが実現されることはありません。企業しても参入障壁のために、 仕事をすることができないためです。
また、政権交代などで参入障壁が撤廃された場合、自由競争の経験のない業界は、 競争に押しつぶされ、価格競争やサービス競争で敗北し、倒産したり品質が悪化する可能性もあります。 民主党政権のころ、電力会社などはヒヤヒヤしたことでしょう。
待遇は良いがホワイトとは言い切れない
参入障壁とホワイトは関係ない!
参入障壁の高い業界は、必ずしもホワイトとは言い切れません。
旧国営企業を始めとした参入障壁の高い業界では、良くも悪くもある程度の利益を確保できる分、 待遇は良く、ホワイト企業が多いです。就職四季報を読むと、その残業時間の少なさや総合職年収の高さがわかります。
ですが、通常の民間事業と比べてビジネスが急成長することもないというデメリットがあり、 「会社が成長して給料が増える」といった民間ならではのワクワクがありません。
こういった企業では仕事の多くは外注しており、総合職はいくつものプロジェクトを取りまとめる役割を果たします。 通常時はホワイトとはいえ、ひとたびトラブルが起きれば責任者として物理的に家に帰れません。
実際にNEXCO西日本やJR西日本では過労死事件が起きています。 (NEXCO西日本:朝日デジタル記事) (JR西日本:デイライト法律事務所)
安易に「ホワイト企業」だと思って入社するのはよくないでしょう。
将来性に乏しい
政治の関わる独占は、国民感情に左右される!
参入障壁があるうちはいいのですが、政府の匙加減1つで外れてしまうものです。 例えばソフトバンクや楽天の新規参入も、政府が乗り気でなければ実現しませんでしたし、 KDDIは「旧国営企業の流れ」があるからこそという側面もありました。
かつては公共事業の談合も「官製談合」と呼ばれるように、 政府の都合で談合をさせていた経緯もありました。しかし、今は談合すれば逮捕されます。
電力自由化で真っ先に電力を食いに行ったのは大阪ガスでした。 関西電力の領域だけでなく東京電力の領域にも進出しています。 これは、大阪ガスはもともと様々な事業をやっている会社で、競争には慣れっこだったからです。
つまり、競争を経験していない会社は、障壁がなくなれば食われるということです。
かつて橋梁メーカーには日本製鉄や三菱重工業、住友金属といった会社がありました。 しかし、2000年代に談合が摘発されると会社数が半減し、上述の会社も撤退していきました。
参入障壁はいつなくなるかわからないために将来性に乏しいという点を覚えておいてください。
昭和の体質が残りがち
「変化しない」ために時代遅れになりがち!
筆者の私も参入障壁のある業界に身を置いていましたが、会社には昭和の体質が残っていました。 いちおう「労基法を守る」という意味では「ホワイト企業」だったのですが、 ハッキリ言って無駄な時間を過ごしたとさえ思います。
社員たちはパソコンやスマホをろくに使えず、2017年になるまでガラケーを使っていました。 仕事では「若手がiPadを持つのは生意気だ」として、いまだに客先に分厚い図面の束を持ち込みます。
そこでは年齢がすべてで、課長や部長であっても、年上の部下に指示ができないという状況でした。 働かない「名ばかり部長」が何人もいて、お酒やゴルフの話ばかりしています。 飲み会では強制一気飲みなど当たり前に行われます。
ですが、これまで困ったことがないので、会社は続いているのです。
能力あるみなさんにとってはこういう会社は力を持て余し、退屈です。 年齢を理由に何もさせてもらえず、無駄な説教を受け続ける日々が待っています。
こんな状況ですから、参入障壁がなくなったとたんに会社が傾くのもうなずけますね。
MY就活ネットでは、この他にも企業選びに役立つリストやランキング記事を用意しています。 優良企業の見落としを防ぐため、さまざまな業界を調べてみましょう。